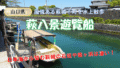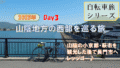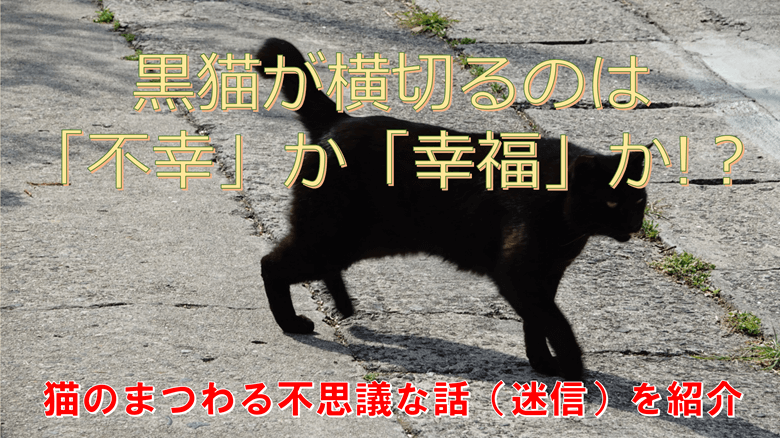
日本で暮らしていると、動物が関わる様々な話を聞く機会が多いです。その中でも私たちに身近な存在として、猫にまつわる話は多い。
猫をペットとして飼っていなくても、旅行へ出かけて見かける機会が多いだろう。そして、その姿に癒されますね。かくゆう私もその中の一人です。
猫にまつわる有名な迷信には、「黒猫が横切ると不吉」があり、誰もが一度は聞いたことがあるだろう。実際のところ本当か嘘と思うのはその人次第。では、この迷信が、なぜ広く広まっているのか不思議に思いませんか。
本記事では、「黒猫が横切ると不吉」の迷信を中心に、旅行中に知って起きたい猫にまつわる不思議な話(迷信)を紹介します。
目次
日本では、なぜ黒猫が横切ると不吉だと思われているのか

もともと黒猫は、現代のように「黒猫=不吉」というイメージがある存在でありませんでした。
平安時代には、夜目が効く動物として魔除けや商売繁盛の象徴とされ、「福猫」として大切にされていたそうです。江戸時代になると、黒猫をペットとして飼うことがブームだったそうな。
特に江戸時代では結核が大流行し、死の病として大変恐れられていたので、黒猫を飼うことで結核が治るという噂が信じられていたといいます。
明治40年頃までは「黒猫=福猫」でしたが、どうやら縁起が悪いイメージになったのには、外国との交流に原因があるみたい。

というのは、中世では黒猫は魔女の使い魔として知られており、不吉の象徴でした。「中世・ヨーロッパ・魔女」のキーワードで連想すると、真っ先に思い当たるのは「魔女狩り」だろう。
実際、中世の終わり頃には、魔女狩りによって多くの黒猫が犠牲になることに。魔女の使い魔として忌み嫌わていたり、暗闇で目だけを光らせる姿が不気味という理由で犠牲になったといわれているのだから、今を知る私たちの価値観では憤慨する人も多いだろうな。
明治時代になり、外国との交流が盛んになり続けることで、当時欧米の黒猫の対するイメージも輸入されたのが、今日における「黒猫=不吉」のイメージにつながっています。
確かに当時の日本は、欧米に「追いつけ追い越せ」というスローガンを掲げ、近代化に邁進していたので、欧米の文化に感化されるのも無理はなかったでしょう。
実は黒猫は縁起が良い!?

現代のヨーロッパでは、黒猫は縁起が良い動物として扱われています。
中世から続いた「黒猫=不吉」のイメージが腐食されたようですね。たとえば、イギリスでは、結婚式を控えた花嫁の前を黒猫が横切ると、幸せになるといわれている。また、恋人がいる人が黒猫に触れれば結婚につながるという。
同じヨーロッパでも南フランスでは、黒猫は「魔法の猫」とされていて、大切に扱うことで幸運をもたらす存在として信じられています。どうですか、中世の頃と比べて正反対のイメージにビックリしますね。
もちろん日本でも、昔のように縁起の良い動物として飼われており、健康運がアップするといわれているみたい。だけど、残念ながら未だに黒猫に不吉なイメージを持つ人は、少なくありません。

不思議な話として、猫は人間のオーラが見えるそうな。なので、良いオーラが見える家に近づくという。こう聞くと「その話、本当なの?」と思いますが、そういうスピリチュアルな話は猫に限らず、様々な動物にありますね。
黒猫が来る家は、近々いいことが起こるそうなので、良い出会いがあるかも知れないかな。また、悪いオーラが憑いている家にも現れて、邪気を払ってくれるそうですよ。なるほど、そう考えると運気が向上することから「黒猫=幸福」と思えます。
猫にまつわる不思議な話(迷信)を紹介
旅行中に猫の愛らしい姿を見かけると、旅行中の高揚感も相まって、より幸せな気持ちになりませんか。普段猫に興味がない人でも、そんな経験があると思います。
猫との出会いにより、何か良いことが起こりそうとポジティブに考えれば、楽しい1日を過ごせるかも。そこで、猫にまつわる様々な不思議な話(迷信)を紹介します。
猫が顔を洗うと雨が降る

猫が前足で顔をぬぐる仕草って、とても愛らしいですね。この仕草を見かけると、ホンワカしてしまいます。
この仕草には不思議ないわくがあり、雨が降る前兆なんだそうな。旅行中に雨が降ってしまうと、スケジュールの変更を余儀なくされる機会が多く、「雨降らないで」と祈る人も多いだろうな。
実は、この行動には少しばかり科学的根拠があるというのだから面白い。猫のヒゲは湿気を測るセンサーの働きをしていて、湿気が高くなると水分を含んでヒゲが重くなるため、それが気になり顔を洗うといわれています。
天気予報のない時代では、先人たちの経験則に基づき将来の天候の予測を立てました。そのため、天気に関することわざがたくさん作られており、現代まで伝えられています。この「猫が顔を洗うと雨が降る」ということわざもその一つですね。
猫は霊が見える

猫が何もない空間を、ジッと見つめる姿を見かけた人は多いと思います。
そういう姿を見かけると、何だか怖く感じませんか。先ほども触れましたが、猫には人間が見えないオーラが見えているという。たまに、人間でもそういう話を聞きますが、霊感が強いのだろうな。
ドイツが第2次世界大戦の最中に行なった実験によると、フェレンゲル博士と愛猫のシュターデンにより、猫が見つめている場所は温度が低いことが分かりました。
さらにナチスの研究によれば、幽霊のいる場所の温度が低くなるということから、「猫は霊が見える」に結びついていると思います。
また、猫の聴力は人間の2~5倍もあるので、人間よりも高い周波数の音や微細な音を聞き取れるそうですよ。ひょっとしたら、周囲の音を聞きとろうとして、ジッとしているのかも知れないですね。
猫は水が入ったペットボトルを怖がる

猫は、水を入れたペットボトルのそばには近寄らないという有名な話がありますが、どうやらこの話は眉唾物で、実際はそんなことはないそうです。
猫は水で体が濡れることを本能的に嫌っているため、この話は生まれたのではないだろうか。臆病な性格の猫であれば、警戒して中々近づかないかも知れませんが、慣れてしまうと効果が全くなくなるぞ。
旅行先では、気持ちが高揚していて普段しなさそうな行為をしてしまうこともあるだろう。だからといって面白半分に、猫の近くへ水が入ったペットボトルを置かないで。ペットボトルに太陽光が反射して、収れん火災が起きる可能性があるので絶対にやめましょう。
収れん火災というのは、虫眼鏡で太陽光を集めて紙を焦がすイメージを想像すると分かりやすいかな。小学生時代に体験した人も多いと思います。
鍵しっぽは幸運を呼ぶ

日本の民間伝承には、尾が二つに裂けた「猫又(ねこまた)」という妖怪が登場します。
猫又は、長寿を全うした猫が妖力を持って妖怪となったそうな。しっぽが長くてまっすぐな猫が、猫又になるといわれていた時期がありました。そのため、短いしっぽや折れ曲がっているしっぽ、いわゆる「鍵しっぽ」の猫が愛されてきた訳ですね。
鍵しっぽは、フック状になっていることから、幸運を引っかけてくれると考えられているみたい。今では幸運を呼ぶ猫として、世界中で大人気ですよ。特に日本では、短い鍵しっぽの猫を飼っていると、より幸運が舞い込むといわれています。
旅行中に鍵しっぽの猫を見かけたら、何か良い出会いや発見があるのかも。その際、猫へ触るのであれば、まず猫の様子をよく観察してみよう。
警戒していたり、嫌がっている様子があれば触らないで。猫がリラックスしている時に、頭やあごの下など触られて嫌がらないところを、そっと優しく撫でて下さいね。そうすれば、より幸運が訪れるような気がします。
神社で猫に会うと歓迎されている

普段、神社へお詣りに行かない人でも、旅行中には名の知れた神社へ参拝する機会は多いですね。
もし神社へ訪れた時、猫に出会ったのならば、それは神様に歓迎されている証拠。その際、まるで先導するように猫が歩いているのであれば、神様に導かれているのでしょう。
これから行う参拝が、あなたにとって必要なのではないだろうか。そういう場面に出くわしたら、素直な気持ちで神様に対して、日頃の感謝をお伝えして下さいね。
神社で猫に出会うと、幸運が舞い込む前兆だったり、悪い憑き物を払ってくれるそうな。そのため、旅行中に立ち寄った神社でバッタリ猫に出くわすと、その嬉しさはひとしおです。
猫が横切る場面に出くわしたら変化の兆候

旅行中に町中や観光地をぶらりと歩いていると、猫が横切る場面に出くわす機会があります。
実はこれ、変化が訪れる前触れなんだとか。つまり、あなたの人生に新たな周期の訪れを告げているといえるでしょう。特に黒猫が横切る場合は、より強い変化があるみたい。
変化を望んでいないのであれば、思わず身構えてしまう気持ちは分かりますが、猫が横切る時に大事なのは、その時の自分自身のメンタルです。
ポジティブであれば、良い変化が訪れるのを期待できるし、反対にネガティブであれば、物事が悪い方向へ進んでしまう可能性があります。
なので、変化を恐れずに受け入れる心構えを持ち続けよう。変化を前向きに捉えて、努力を積み重ねていれば、より運気は上昇するでしょうね。
まとめ

「黒猫が横切ると不吉」という迷信は、根拠のない話であり、本来黒猫は福を呼ぶ存在でした。外国から持ち込まれた「黒猫=不吉」というイメージが広まった結果、現代まで語り継がれているようです。
猫好きの人からしたら、腹立たしい話でしょう。本記事では、猫にまつわるたくさんのある話の内、ほんの一部を紹介しました。素敵な話や不思議な話、それに夢のある話まで、様々な迷信や噂がたくさんあるので、くわしく調べてみるのも楽しいですね。
旅行中に猫を見かけたら、いつでも「幸運の印」とポジティブにとらえていた方が、より旅行を楽しめます。