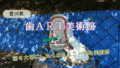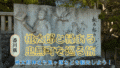自転車のフレームとハンドルは、「ステム」というパーツでつないでいます。
ステムの長さや角度により、ハンドルの位置が決まるため影響度も大きい。特にロードバイクでは、前傾姿勢で走行するため、走りやすさに直結するほどですね。
そのような重要なパーツなのですが、初めてロードバイクを購入した時に取り付けられていたステムを、そのまま使い続けている人も多いだろう。ロードバイクの交換パーツの中でも、見落としがちなパーツですよ。
そのためか、本当にそれが今の自分にとって、ベストな状態なのか中々気付きにくいです。
本記事では、ステムの役割や選び方を始め、ステムを変える影響について紹介します。
目次
ステムの役割と種類

ステムは、フレームとハンドルをつなげてハンドルとの距離を調整する役割があり、運転時の姿勢に影響を及ぼします。
サドルに座ったポジションから、ハンドルまでの距離や角度を調整すれば、安定した高速走行もしやすくなる。さらに調整次第では、ブレーキレバーの操作がしやすいため、安全性の効果も大きい。
また、ドロップハンドルではなくフラットハンドルを採用するならば、低速時により安定した走行ができます。
つまりステムは、快適なライディングポジションを決めるのに、欠かせないパーツですね。ステムの種類には、大きく分けて以下の2つがあります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| アヘッドステム | ・ロードバイクなどスポーツ自転車に良く使用される ・軽量で雨風に強く、長期間のメンテナンスが不要 ・着脱が非常に簡単なため、カスタマイズしやすい ・ステム自体で高さの調整はできない |
| スレッドステム | ・ママチャリなど一般的な自転車に採用されている ・下に長く伸びた形状が特徴的 ・頑丈で高さの微調整がしやすく汎用性に優れる ・重量が重くなりがちなので、軽量化には向かない ・比較的緩みやすくなるため、前傾姿勢には向かない |
ロードバイクなどスポーツ自転車のアヘッドステムは、種類が豊富なので自分にマッチするものが選びやすくなっています。
なので、ロードバイクを購入する際には、最初から自分の高さに合うステムを選択しましょう。
ステムの交換は乗車姿勢や視界に影響が大きい

ハンドルまでの距離や高さが変わると、乗車姿勢が変わります。
より前傾姿勢が取れるポジションにしたり、反対にアップポジションにすることで、視線や視界が全然違ってくる。視界は安全に走行するために重要な要素なので、高さを低くする際には無理のない範囲で行って下さいね。
また快適さが違ってくるので、長時間のライドでは影響が大きいです。ステムの長さや角度によっては、ママチャリに近いポジションにすることもできます。
それに乗車姿勢が変わることは、ペダリングにも影響が出てくるから気を付けよう。なので、自分が最も快適に走れるライディングポジションに調整して下さいね。ペダルに力を入れやすくなれば、疲れにくくなります。
ステムの選び方
ステムを選ぶ時に確認すべき主なポイントを、以下にまとめました。
- ハンドル径とコラム径を確認する
- 長さと角度を確認する
- 素材を確認する
- メーカーを確認する
それぞれについて説明します。
ハンドル径とコラム径を確認する

ハンドル径とは、言葉通りに自転車のハンドル部分の直径を表します。一方、コラム径とは、フロントフォークの上部にあるステムが取り付けられる筒状の部分の直径ですね。
まずは、この2つの規格を確認しよう。対応していないステムでないと、そもそも装着できないです。
ロードバイクの主なハンドル径とコラム径は以下の通り。
- ハンドル径
- 25.4mm、31.8mm(よくあるハンドル径)
- その他にも35.0mm、31.7mm、26mm、25.8mmなどがある
- コラム径
- 28.6mm(1-1/8インチ規格)・・・オーバーサイズ、ロードバイクの主流
- 25.4mm(1インチ規格)・・・・・ノーマルサイズ、クロモリバイクに多い
- 31.8㎜(1-1/4インチ規格)・・・スーパーオーバーサイズ、メーカー独自のものが多い
- 38.1㎜(1.5インチ規格)・・・・ワンポイントファイブ、ロードバイクでは珍しい
シムというパーツを使用すれば、規格外のハンドルでも装着できる場合があります。たとえば、31.8㎜規格のステムでは、シムで隙間を埋めることで、25.4㎜のハンドルを取り付け可能だ。
また、まれにメーカー独自のハンドル径を採用していたりするので注意すること。特に注意しておきたいのが、DEDA製の規格である31.7mmです。
というのは、主流の31.8mmと比べてわずか0.1mmしか違いがありませんが、無理やり取り付けると、剛性に影響を与えてしまう可能性があるという。その結果、破損や事故につながることもあるので、無理な取り付けは絶対にやめましょう。

フォーク側にとりつけるステムの高さを「コラムハイト」といいます。
一見、どのステムも同じような高さに見えるのですが、メーカーにより微妙に違っている。ステムを交換してから「何だかハンドルがガタつくけどなぜ?」と思うならば、この微妙な差が影響しているかも知れません。
コラムの高さは、コラムスペーサーを使い高さを調整します。たとえば、コラムハイトが40mmのステムを取り付けたいのだけど、現行42mmであれば、2mmのコラムスペーサーを追加して下さいね。
長さと角度を確認する

ハンドル径とコラム径の確認を終えたら、自分の好みや目的にあった長さと角度のステムを選びましょう。
長さを変更すると、ハンドルの前後位置が変わり、角度はハンドルの上下位置を調整できる。長さは50~130mmのモデルが多く、角度は一般的に0~35度のモデルがあります。
ステムの長さは、短くなるほどハンドルが近くになり、アップライドの姿勢になりやすい。反対に長くなるほど、ハンドル位置が遠くなるので、必然的に前傾姿勢の強い体勢になる。
自分の身長や体型に合わせて選んで下さいね。わずか10mmの違いでも影響度は大きいですよ。

また、長さだけでなく角度も重要です。ステムの角度が浅くなると、ハンドルの位置が下がるので前傾姿勢が強くなり、逆に角度が深くなるとハンドル位置が上がるの、上体が起き上がります。
ステムの角度は、6度・7度・17度のものが多い。一般的にフォークが地面に対して73度くらいの傾きがあるので、17度のステムを使うと、地面に対してステムが平行になる。個人的には、ロードバイクを横から見た時に、一番カッコイイと思います。
実際、角度がどの程度が良いのかは、ロードバイクのフォークの角度によって左右されるだろう。また、ステムの構造上、上下を反転して使えるぞ。慣れるまでは上向きに使うのもアリかな。
もしロードバイクの走行中に疲れやすいのであれば、今装着しているステムを短くして、角度の深いモデルに変更してみよう。そうすることで、改善される可能性があります。
素材を確認する

ロードバイクで使うステムの主な素材は「アルミ」か「カーボン」です。その他にも「チタン」や「クロモリ」があります。
アルミは耐久性や防錆性、軽量性に優れ、コストパフォーマンスも良し。完成車に標準装着されるステムに多いです。
一方、カーボンはアルミより軽く、振動吸収性に優れている。そのため、レースなどスピードを第一に考えるならばこちらの方が良いでしょう。
アルミ製のモデルとカーボン製のモデルでは、それほど軽さに違いがある訳ではありませんが、急坂ではダンシングすることで、その違いを感じ取ることができると思います。
ちなみに、チタンは軽量で耐久性がある素材ですが、価格が高めなのがネックかな。個人的には、特にこだわりがないのであれば、比較的低価格なアルミ製のステムで十分だと思います。
メーカーを確認する

ステムは、開発メーカーによってデザインや耐久性、価格などが違っています。また、ハンドルとの相性があることも。同じメーカーのステムとハンドルは相性が良いという話は、よく聞きますね。
メーカーを選ぶ際には、デザインだけでなく自分が求める特徴や用途にあうモデルがあるのかが大事となる。
とたえば、3Tはプロ向けの製品を多く開発しており、実際にプロチームが使用しています。軽量でお洒落なモデルであれば、DEDAのステムが良いかも。
その他にもシマノプロやデダエレメンティ、チネリなど多くのブランドがあります。
ロードバイクで使いたいステムの紹介
ロードバイクで使いたい様々なステムを、下記関連記事で紹介します。
ステムとハンドルが一体化したモデルもある
ハンドルと一体化したステムは、サイズ調整や角度調整ができません。一見するとデメリットばかりが目に付きやすいですが、一体化することで、剛性の向上や空気抵抗の削減が期待できます。
ただし、調整ができないということは、サイズが自分にピッタリと合っていなければ使いづらい。レースなどで速く走ることに拘るのであれば、選択肢の一つとして考えてみるのも良いと思います。
まとめ

本記事では、ステムの役割や選び方を始め、ステムを変える影響について紹介しました。最後にもう一度、ステムの選び方を以下にまとめます。
- ハンドル径とコラム径を確認する
- 長さと角度を確認する
- 素材を確認する
- メーカーを確認する
ステムはロードバイクの交換パーツの中でも、見落としがちですが、乗車姿勢に与える影響は大きい。交換した結果、視界や乗りやすさが交換前とは全然違ってくるなんて、普通にあり得ます。
必要に応じてステムを交換して、ロードバイクを自分好みにカスタマイズして下さいね。