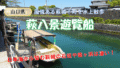旅行へ出かけると、様々な乗り物で移動する機会が増えてきます。
たとえば、自家用車やバス、タクシー、電車、船、飛行機など日常的に利用する乗り物から、普段はあまり利用しない乗り物まで、目的地まで移動するのに欠かせません。
2023年に大正製薬が行った乗り物酔いを自覚している人約1,750人に対して、インターネットでアンケートをした結果、約8割の人が4回に1回以上は乗り物酔いするという回答がありました。
つまり、それだけ乗り物酔いに悩んでいる人が多いということです。かくゆう私も乗り物酔いをしやすい体質のため、他人事ではないですね。ということで、乗り物酔いについて調べた結果を、まとめることにしました。
本記事では、乗り物酔いしやすい人の特徴とシチュエーションを紹介します。
目次
どんな乗り物が酔いやすいのか

冒頭で旅行に利用する乗り物をあげましたが、どれもが酔う可能性があります。
調べてみると、乗り物によっては酔う頻度が違っているようで、多くの人は「船」「飛行機」「長距離バス」に酔いやすいことが分かりました。
個人的には、自家用車やバスが多いだろうなと思っていたのですが、これは意外でしたね。その理由は、日頃から頻繁に利用していない乗り物なので、それらの「揺れ」に慣れていないということ。確かに納得感があります。
特に船は、立ってられない激しい揺れを感じ続けると、一気に気持ち悪くなる。船上は逃げ場がないので、まさに生き地獄ですね。
どんな乗り物も長時間乗っていると、酔ってしまう可能性が高くなります。たとえ乗り慣れた「車(自家用車やバスなど)」でも酔う頻度がかなり高いですよ。かくゆう私はバスがNGであり、1時間以上も乗り続けると、酔わない自信がないですね。
乗り物酔いしやすい人の特徴

乗り物酔いがしやすい人には、共通の特徴があります。
一般的には、年を重ねていくにつれ様々な乗り物で移動する経験が増えてくるので、酔わなくなってきますが、普段から乗り物に乗る機会が少ない人は、大人になっても酔いやすいままです。
また、乗り物に対する強い精神的ストレスを抱えている人も酔いやすいですね。対象の乗り物にトラウマを抱えていると、どうしても恐怖心が出てしまうのは避けれません。
つまり、酔いやすい人の特徴というのは、乗り物に対する経験値不足といえるでしょう。実際、体質に個人差があるので、経験だけではどうにもならない壁がありますが、それでも経験を重ねていけば、比較的マシになってきます。

三半規管や脳の働きが未発達な乳幼児(2歳頃まで)では、乗り物酔いをしないという。その後、体質や脳の情報処理能力などが影響して、酔いやすくなるそうですよ。一般的には、小学校に通う6歳から12歳頃までの学童期に、乗り物酔いのピークがくるみたい。
私も確かに小学生の時が酷かったかな。修学旅行などで長距離バスへ乗る機会があり、車酔いが酷く片時もエチケット袋を手放せなかったですね。
乗り物酔いをするシチュエーション

バスや船、電車などの乗り物に乗って、目的地まで何もせずに過ごすという人は稀でしょう。
目的地まで時間があれば、何かしらのアクションを行なっているものですね。たとえば、スマホを見ていたり、読書したり、ゲームを楽しむことも。実は、これらは、より酔いを誘発しやすい原因になります。
乗り物酔いがしやすい人は、子供も大人も関係なく「スマホ・読書・ゲーム」はしない方が無難かな。といっても、時間を潰すのに持って来いのものばかりなので、程度をわきまえて楽しみましょう。
また、乗り物酔いで不快に感じるのは、「揺れ」「匂い」「空気」の3つが多い。揺れは言わずもがな。匂いには色々ありますが、タバコや芳香剤、ゴム、ガソリンなどを苦手とする人が多いといいます。
それに、空気が淀んでいると酔いやすくなるので、車の窓を開けたり、船のデッキに出たりして、新鮮な空気を取り入れよう。
その他にも車内や船内の温度が快適でないと、酔いやすくなる。乗り物の環境は、換気により新鮮な空気が充満していて、無臭なのが一番良いですね。
乗り物酔いの症状・原因

乗り物酔いの症状と原因については、以下の下記関連記事で紹介します。
こちらの記事では、自転車酔いについて紹介していますが、自転車は車やバスと同じく乗り物です。そのため、乗り物酔いの症状と原因自体は同じになる。
ただし、酔った後の対処方法は、他の乗り物と若干違っているぞ。というのは、自転車は自分で運転するのに対して、バスや船などは自分以外の他人が運転するからですね。
乗り物酔いの主な対処方法

乗り物で酔ってしまった時の対処は人によって様々ですが、調べた結果では「窓を開ける」「酔い止め薬を飲む」「遠くの景色を見る」が多かったです。
これらは予想できていたので、その通りだなと思いました。その他にも色々ありますので、対処方法を以下にまとめて紹介します。
- 窓を開ける
- 酔い止め薬を飲む
- 遠くの景色を見る
- 寝る
- 音楽を聴く
- ベルトや服を緩める
- 自分で運転する(ほぼ自家用車限定)
これらの内、「寝る」に注目しよう。寝るという行為は、目を閉じて誰とも喋らなくなる。
つまり、視界と体の情報のギャップがなくなるし、無理に話して吐き気が増すこともない訳だ。それに、何より寝てしまえば意識がなくなるので、具合の悪さを気にしなくなるぞ。
実際、私も車で乗り物酔いした時は、窓を開けて寝ていることが多いです。
また、周囲の状況にもよりますが、乗り物酔いによる吐き気は、意外に我慢しない方が楽になることも。すぐにトイレへ駆け込めるならば、一度吐いた方がスッキリするでしょう。
吐き気がしばらく続く場合があるので、しばらくはトイレから動けなくなると思います。(私も経験あり)
酔い止め薬の紹介と注意点

一般的に酔い止め薬は、乗車の30分~1時間前に服用するのが効果的です。
飲むタイミングや薬の種類によって効果が異なっており、酔ってしまった後に服用しても、症状を緩和する一定の効果が期待できますね。
酔い止め薬に含まれる成分には、主に脳の中枢に作用して、自律神経のバランスを整えてくれるそうな。そのため、吐き気やめまい、消化管の動きを抑制する効果があるという。酔い止め薬は、まさに乗り物酔いをする人にとっては、救世主のような存在ですね。
そこで、薬局などで良く販売している酔い止め薬を紹介します。
- センパア プチベリー(大正製薬)
- センパアPro(大正製薬)
- アネロン「ニスキャップ」(エスエス製薬)
- トラベロップQQG(浅田飴)
- トラベルミン(エーザイ)
多くの酔い止め薬は、服用すると眠くなってくるので、自分で運転するならば気を付けること。他の薬と飲み合わせする際にも注意が必要です。気になる方は、薬剤師に相談するように。間違った服用は怖すぎます。
それに、薬は水かぬるま湯で服用するのが基本です。お茶やジュースで服用するのはNG。さすがにお酒で服用する人はいないだろうな。
大人と子供では、必要とする成分と量が違ってきますので、説明書をよく確認して下さいね。子供は大人より薬の影響を受けやすいです。子供用の酔い止め薬も販売しています。
まとめ

旅行中に乗り物酔いをすると、旅行そのものが楽しめなかった思い出になることが多いです。
酔いが酷くなると、気持ち悪すぎて嘔吐してしまうので、辛い気持ちの方がずっと残りやすい。これは、経験したことがない人には、分かりずらいだろうな。
乗り物酔いをする人は、体質的なものであったり、疲労や睡眠不足が原因で引き起こります。後者は自分で気を付けれますが、前者は上手に付き合っていくのが無難ですね。(または体質改善を頑張る。)
様々な乗り物に乗って経験を積むことで、酔ってしまうラインを見極めることが大事。もし酔ってしまったら、症状が軽い内に対処すれば回復も早いです。