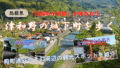日本全国には、京都に似た風情を持つ「小京都」と呼ばれる町がたくさん存在しています。
その中でも「山陰の小京都」と呼ばれるのは、津和野町(島根県)・萩市(山口県)・倉吉市(鳥取県)などを挙げる人が多いだろう。
以前の自転車旅では、倉吉市へ訪れたことがあるので、今回は津和野町と萩市を観光しようと思いました。そこで、3泊4日の計画を立て、主に山陰地方の西部や日本三大カルストの一つに数えられる秋吉台などを巡ります。
旅の初日は、新幹線や電車を乗り継ぎ、やってきたのが山口県の長門峡駅。いきなり津和野町の玄関口となる津和野駅へ向かうよりも、そこは自転車旅なので、旅の道中もゆっくりと見て回りたいですね。なので、石州瓦の住宅と田園が織りなす景色の中を駆け巡るぞ。
本記事では、長門峡(ちょうもんきょう)から島根県の津和野町を目指す、旅の様子をお届けします。
目次
道の駅で腹ごしらえをして長門峡へ向かう

空を見上げると、気持ちの良い青空が広がっています。
私が今いる場所は、山口県山口市阿東生雲東分にある長門峡駅。国指定名勝・長門峡の最寄り駅ですね。
もちろんこの場所を自転車旅のスタートに選んだ理由の一つが、長門峡の存在なのは言うまでもありません。長門峡は、山口県中部にある阿武川中流の渓谷であり、変化に富んだ美しい自然景観が特徴なんだとか。
それに、渓谷沿いには遊歩道が整備されているので、阿武川の清流を始め、奇岩・滝などを間近に見物できるというのだから、絶対に楽しいに決まっています。

既に時刻は11時を過ぎていて、昼時ということもあり、旅を始める前に腹ごしらえをすることにしました。駅から約350mほど国道9号を西へ進むと、道の駅があるので入ることに。(事前に調査済みですよ。)
ここで気が付いたのは、チェンソーアートの作品が多いこと。丸太をチェンソーを使って作る彫刻の見事さに感心しながら、一つ一つの作品の見て回ります。



道の駅の奥へ向かい「お食事処 長門峡」へ入ると、メニューを見て何を食べようか考える。
どうやら、あとう和牛を使ったすき焼きセットや牛丼などがおすすめのようで悩みましたが、私が選んだのは「天とじ丼セット」です。

天とじ丼セットは、個人的に好きな物の上位にくるのだからしょうがないでしょ。
うん、やはり天ぷらの風味と卵の優しい味わいが素晴らしい。セットでボリューム満点というのもありがたいですね。

あっという間に完食すると、少し道の駅内を見学します。そこで見つけたのが、アニメ「ざつ旅」を紹介しているではないですか。
ざつ旅は、主人公・鈴ヶ森ちかがSNSのアンケート結果を元にして、行き当たりばったりな旅をするお話。丁度、アニメの鑑賞をしていたので、私にとっては実にタイムリーでしたね。
旅人の私には共感する話が多くて面白い。それに名所などを紹介してるのもいいですね。旅好きな人は、きっと気に入ると思います。

さて、それではそろそろ長門峡へ向かいますよ。
道の駅から萩長門峡線(県道293号)を北へ向けて少し自転車を走らせ、篠目川に架かる橋を渡ると右手側に遊歩道を発見。
自転車を道の駅に置いておいて来た方が良かったかなと考えていましたが、それは杞憂に終わりました。

というのは、通行止めになっていたからです(シクシク)。それはないでしょ。
たしかに本日の最終目的地である津和野町の観光スポットは、じっくりと調べましたが、長門峡については、本格的に散策するつもりがなくて、あまり深く調べていない。
まさか通行止めになっているとは、思ってもいませんでした。これはシュタインズゲートの選択か、それとも神のお告げなのか。まっ、なんせよ諦めるしかないです。

それでも長門峡のさわり部分だけでも見物できたのが救いかな。阿武川の風景に癒されます。
その後、国道9号線へ合流すると、津和野町のある東へ向けて自転車を走らせました。
石州瓦の住宅が織りなす風景の中で

津和野町までの主なコースは、国道9号線から篠目徳佐下線(県道311号)へバトンタッチして、再び国道9号線を経て入る予定です。
全般的になだらかな坂道が続き、道なりに進むならば時折6%前後の急坂がある程度なので、自転車旅になれていれば楽勝といえるだろうな。約40kmのコースなので、時間的な余裕もかなりある。
長門峡の観光がダメになったこともあるし、その分津和野町を観光する時間が取れるという訳。旅へ出かけたならば、ポジティブに考えるのが大事ですよ。



たくさんの石州瓦の住宅を見かけると、「今、山陰地方を旅しているのだ!」という実感を得ますね。田園風景の中に、特徴的な色合いを持つ赤褐色の石州瓦が良く映えており、大自然と調和しています。
私が住んでいる地域では、そのような景観は見られないので、山陰地方へ訪れるたびに新鮮な気持ちになるぞ。

それに加え、山口県といえばオレンジ色(夏みかん色)のガードレールでしょ。県道のガードレールで見かける機会が多いかな。
県の特産品である夏みかんをアピールする狙いがあったそうですが、とても目立つ色なので、山の緑に映えて、視認性が高いので機能性もバッチシ。いいことづくめのガードレールです。
しばらく道なりに進んでいると、たくさんのリンゴ園を見かけました。

リンゴの木を見ると、白い花を咲かしており、思わす「ラッキー!」と声が漏れる。リンゴ園がない地域では、見かける機会なんてそうそうないのだからさもありなん。こういう偶然に感謝、感謝!
ちなみに、リンゴの花は桜の花が咲き終わる頃に咲き始めます。どうせならネット越しでなく、間近で花をみたいぞ。そう思って、良さそうな場所を探していると、意外とあっさりと見つけました。

ジャジャジャジャーン。どうですか、可愛らしいでしょ。リンゴの花は、白い花びらにピンクの蕾が特徴なんだとか。甘酸っぱいような香りがします。
香りをかいでみたかったのですが、そこまで近づくとなると、園内へ入ってしまうので、勝手に入るのは流石にアウトですね。
しばらくの間、リンゴの花を見て時間を過ごしました。
船平山展望台から眺める田園風景

田園が織りなす風景を横目で眺めながら、自転車を走らせます。
田園風景を見ていると、癒される人が多いでしょう。もちろん私もそうなので、その気持ちはよく分かる。穏やかで自然豊かな景色というのは、リフレッシュに持って来いですよ。
青空の下、広がる緑の中に点々と建つ木々や家屋の風景は、視覚的に気持ちがいい。それに加え、風の音や土の匂い、鳥のさえずりなどといった田園地帯でしか味わえない自然の音や香りは、私たちに癒しや安心感を与えてくれます。


阿東徳佐上地域には、田園風景の中でSL(SLやまぐち号)が疾走する姿を見られる展望スポットがあるということで、そこへ向かうことにしました。
その場所は、標高431mの船平山山頂付近にある「船平山展望台」です。徳佐盆地が一望できる絶景スポットなんだそうな。まぁ、SLやまぐち号は、土日祝日を中心に運行するので、本日(平日)は見られないだろうな。
それでも絶景スポットということで、どのような眺めなのか見てみたい。それだけで訪れる理由としては十分ですね。

しばらく線路沿いの道を走っていると、見えてくる住宅が少しづつ多くなってきました。そして、遮断機の向かう側へ渡り、田舎の住宅街の中を進んでいると、船平山展望台の案内板を発見。
どうやら、この細道の先に展望台があるようです。


自転車なので、道幅は全然問題ありませんが、それよりも路面状態が悪すぎる。
それに加え、劇坂すぎるぞ。サイコンで確認すると、なんと勾配が19%と表示しているではないですか。さすがに19%はないでしょ。体感的には15%前後だと思ったので、おそらく一時的なバグだろうな。(電波状態の問題かしら?)

そんな感じで上り続けると、頂上付近に展望デッキらしいものが見えてきました。
まだ劇坂が続きますが、苦労して上りきると、その道中からは眼下に徳佐盆地が広がっています。山間で、これだけの広い盆地というのは、なかなか見かけないのではないだろうか。



田園が織りなす絶景に拍手喝采を贈りたい。この景色を見ているだけで、日々の疲れが吹き飛ぶでしょう。それに、まるで時間が止まっているような感覚に陥るかも。
しかしそれは錯覚であり、田んぼの上を風に流された雲が、ゆっくりと移動していることから、時間が進んでいるのが分かります。

展望デッキの奥へ顔を向けると、なだらかな斜面の上には「ふれあいハウス」という名前の小屋を発見しました。
小屋へ向けて歩いていると、下から車の走行音が聞こえてくる。次々と車がやってきて、小屋の前に停まります。なるほど、どうやら「ふれあいハウス」は盛況でなによりですね。

船平山は絶景スポットだけでなく、山口市の天然記念物であるユウスゲやレンゲツツジの群生地なんだそうな。その他にもワラビやツツジの宝庫だそうです。
特にユウスゲは、船平山を代表する花として、7月中旬~8月上旬に見頃を迎え、約1ヘクタールに渡り群生を見られるという。
夕方に開花して、翌日の昼には閉じるそうなので、機会があれば一度見てみたいですね。
津和野市街へ向かう前に道の駅で一休み

船平山から津和野町までは、もう10kmも離れていません。時間に余裕があるし、「道の駅 長門峡」からここまでまだ一度も休憩を取っていないので、少し休憩を取りたいと思いました。
Googleマップで確認すると、津和野町へ入る直前に「道の駅 願成就温泉」があるみたい。ということで、これは行くしかないでしょ。
「そんなことせずに、真っすぐ津和野市街へ向かえばよいのでは?」という声が聞こえてきそうですが、その時に思った感情のまま行動するのも、旅の楽しさの一つです。
寄り道することで、予想もしていない出来事に遭遇したり、面白い体験ができたりします。ということで、「道の駅 願成就温泉」へ向けてレッツゴー♪




「道の駅 願成就温泉」は、名前の通り温泉施設と道の駅が一体となった施設です。
日帰り温泉や特産品の販売、レストランなどがあります。日本庭園風の造りの露天風呂があるみたいで、興味を注がれますが、少し休憩するつもりなのでパスすることに。

足湯が無料で入れるのが素晴らしい。入浴しなくても、足湯ならサッと利用できるのが利点ですね。
それに足拭きが用意されていて、こういう細かな心配りに感心します。


エントランスへ向かう途中で面白いものを発見。それが、こちらの「ねこ地蔵」と「干支の地蔵」たち。どうらやら、猫は干支に入っていないので、少し離れた場所にいました。
ねこ地蔵は、屋根付きの建物の下で祀られており、特別感を感じます。さらに猫絵馬コーナーや猫おみくじなど、猫関連のものが多い。
可愛いお姿のお地蔵様たちに、思わずカメラのシャッターを切っていたかしら。この道の駅へ訪れる機会があれば、ぜひ会いに行ってみて下さい。
撮影会を終えると、ソフトクリームを食べながらゆっくりと休憩しました。

さて、それでは自転車旅の再開です。「道の駅 願成就温泉」から約250m進むと、野坂トンネルが見えてきた。
野坂トンネルは、山口県と島根県の県境に位置しており、トンネルを抜ければ、そこはすでに津和野町ですね。道の駅でしっかり休んだので、気力も体力も充実している。
この状態ならば、ノンストップで津和野観光が楽しめそうです。

野坂峠を越えてしばらくすると、高さ18mもある巨大な朱塗りの鳥居が、目の前に立ちはだかりました。どうやら太皷谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)の鳥居のようだ。
なるほど、これは津和野を訪れる人たちにとっては、旅の始まりを象徴する存在ですね。ということで、鳥居をくぐり抜け、その先の坂道をいっきに下ると、ついに津和野市街へ入りました。
山陰の小京都・津和野の城下町を歩く

津和野町は、四方を山々に囲まれた盆地に位置しています。13世紀には津和野城の城下町として栄え、この地方の産業・文化の中心地でした。
メインストリートとなる殿町通りには、今も白壁の土塀や掘割(水路)、上級家臣の武家屋敷の表門などが残されており、見どころが多い。ちょうど私が殿町通りに到着した時には、多くの観光客がガイドの案内の元、観光していましたね。
さすがは年間100万人の観光客が訪れる町だけあります。
また、殿町通りの奥に続く本町通りの町並みも素晴らしい。重厚な造りの商家が数多く残されているぞ。





どれくらい時間を費やしたのか分からなくらい、カメラを片手に歩き回り、城下町やその周辺の見物に没頭しました。
特に太皷谷稲成神社は、麓から標高214mの境内まで263段の石段が続き、約1,000本の朱塗りの鳥居をくぐり抜けながら歩いたので、感慨深いですね。
それに、境内から見下ろす津和野の町並みはお見事の一言。



本日中に霊亀山上に築かれた津和野城跡へ行こうと思いましたが、帰路のリフトの最終時刻に間に合わないようなので断念。まぁ、明日の午前中も津和野観光をする予定なので、問題ないだろうな。
ということで、夕暮れ時まで津和野の町を観光。こうして、本日の旅は終了しました。
津和野の城下町エリア及びその周辺の観光スポットや、太皷谷稲成神社については、下記関連記事でくわしく紹介します。
まとめ

本日は、良く晴れた旅日和の1日でした。
道の駅で昼食を食べて長門峡へ向かうと、まさかの遊歩道が通行止めになっているというハプニングがありましたが、それ以外は順風満帆な旅を続けられましたね。
津和野町へ向かう道中では、赤褐色の独特な石州瓦の住宅を見かける機会が多く、そのたびに山陰地方を旅している実感を得ます。それに青空の下、田園風景の中を自転車で疾走するのが楽しかったです。
津和野町へ辿り着いてから、殿町通りや本町通りを歩きながら、津和野町の歴史と文化を学びました。さらに約1,000本もある朱塗りの鳥居が印象的な太皷谷稲成神社や、鷺舞神事で有名な弥栄神社を参拝して過ごした次第です。
さて、明日の午前中は、本日に引き続き津和野町を観光して、午後からは山口県にある小京都・萩市を目指して旅をするぞ。どんな旅になるのか、乞うご期待!!