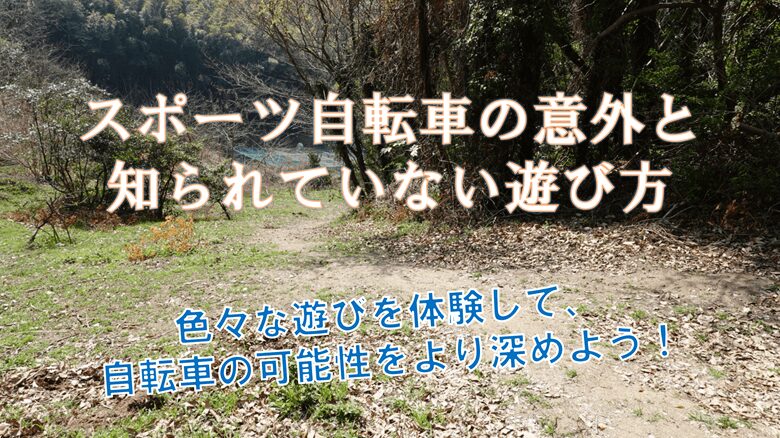
スポーツ向けの自転車には、ロードバイクを始めクロスバイクやマウンテンバイクなど様々な車種があります。
主にサイクリングで活用されますが、サイクリング以外にも色々な遊び方があるのを知っている人は少ないのではないだろうか。
たとえば、「サイクルロゲイニングを知っているか?」と質問しても、「何それ?」「ロゲイニングなら知っている」と答える人が多いだろう。
色々な遊び方を知っていると、より自転車の面白さの幅を広げられるものだ。なので、機会があればサイクルイベントへ参加して、ぜひ体験して下さいね。
本記事では、スポーツ自転車の意外と知られていない遊び方について紹介します。
目次
自転車はサイクリング以外にも面白い遊び方が多い

自転車は、日常の移動手段として活用している人が多い乗り物です。それ以外にも通勤通学や健康維持、シェアサイクルなど多岐にわたり利用されています。
また、地域活性化を目的にサイクルイベントが開催されているのを知っている人も多いだろう。
サイクルイベントには、ロードレースやヒルクライムのように同じ趣味を持つライバルと競い合う自転車競技を始め、ロングライドやセンチュリーライド、ブルベなどサイクリング系のイベントも多いですね。
普段からロードバイクやクロスバイクに乗って、自転車趣味を楽しんでいるのであれば、そのようなイベントに一度は参加した経験があるのではないかと思います。
サイクルイベントの中には、「走る+α」の楽しみ方ができるものもあり、そのようなイベントは意外に知られていないので、以下に主なイベントをまとめました。
- サイクルロゲイニング
- トレイルライド
- シクロクロス
- スノーサイクリング
- ライドハンターズ
これらのイベントは、名前を聞いてもピンと来ない人が多いと思いますが、どのようなイベントか知ると「楽しそう!」と思うだろうな。
それでは、それぞれについて説明します。
サイクルロゲイニング

サイクルロゲイニングは、一言で表すと「自転車 + オリエンテーリング」です。
つまり、自転車を使ってあらかじめ決められたチェックポイントを巡り、時間内に獲得した得点を競うゲームですよ。一般的には、1チームは2~5人ほどで組み、競技時間は長ければ24時間、短いものは2時間ほどで行ないます。
チェックポイントにより点数が違っていて、見つけにくかったり、たどり着くことが難しい場所には高ポイントが加算される仕組みとなる。
効率よくポイントを稼ぐには、地図を見ながらチェックポイントを巡るコースや順番を考える必要があり、体力と知力だけでなくチームワークも重要だ。
どうですか、面白そうでしょ。ロードレースもチーム競技ですが、それとはまた違った戦略性が必要。子供から大人まで楽しめるイベントですね。

歴史遺産や地元グルメの飲食店などをチェックポイントとして巡る機会が多く、特定の観光地や地域で開催されています。
たとえば、「サイクルロゲイニングFKS2IBR」や「サイクルロゲイニング in 北霧島」などがある。くわしくは公式サイトで確認して下さいね。
ちなみに、Google検索で「サイクルロゲイニング 公式サイト」のように入力して検索すると、色々な大会情報が表示されます。
トレイルライド

トレイルライドは、簡単にいえばマウンテンバイクで山道や林道などの舗装されていない道(オフロード)を走ることです。
舗装路とは違い、路面には砂利道や葉木の根、岩場があったり、自然そのものの環境を走るので、路面状況に対応する運転テクニックが求められます。
当然そのような環境なので、頑丈なフレームや太いタイヤを持つマウンテンバイクが必要。服装は、ヘルメットやグローブを当然として、ヒジやヒザにはプロクテクターをして、汚れてもよい服装が好ましい。
持ち物には、パンク修理キットや補給食、水、救急セット、虫よけスプレーなどが必要。というのは、舗装路よりもパンクがしやすいし、転倒リスクが高いからですね。
急斜面を下るときなんて、ドキドキものですよ。スリルだけでなく、ロードバイクとはまた違った爽快感を楽しめます。

代表的にイベントには、シマノ・バイカーズフェスティバル内の「Trail Ride+(トレイルライドプラス)」があるので、気になる方はぜひ参加してみよう。
もちろんイベントではなく個人でも楽しめますが、走行前には必ず進入禁止エリアを確認し、自分のレベルに合う場所を走ること。また、土地の所有者やハイカーにも配慮が必要です。
転倒などで自走できない状態になると、消防やレスキューのお世話になることもある。スマホが圏外の可能性もあるので、基本的に単独行動は避けましょう。
シクロクロス
シクロクロスは、舗装路だけでなく土や芝、砂利、泥などあらゆる路面を織り交ぜたコースを走る周回レースです。
コースには、柵や階段などの障害物があるため、必要に応じて自転車を担いで越える必要がある。小学生の運動会の障害物競争をイメージしそうですが、こちらの方は何十倍も過酷ですね。
もともとは、1900年代のヨーロッパにて、ロードレース選手のオフシーズンのトレーニングとして始まりました。そのような経緯があるため、今でもロードレースのオフシーズンとなる11~2月に行われることが多い。
1周2.5~3.5km程度の距離を走り、時間制(30~60分)で行われる。自分の身体能力やテクニックがダイレクトに反映されるので、トレーニングの成果が楽しみな人も多いだろうな。
また、見る側にとっては、選手が変化する路面を走り抜く様子を間近に観戦できるのが面白い。周回コースなので、何度も目の前を通過するのも応援のしがいがあるというものですね。
日本シクロクロス競技主催者協会(AJOCC)の公式サイトを確認すると、様々なシクロクロスの大会を確認できます。たとえば、「シクロクロス東京」や「幕張クロス」などがあり、気になる大会があればチェックしてみよう。
スノーサイクリング

スノーサイクリングは、自転車で雪道や雪原を走るスポーツです。名前からしてイメージできる人が多いと思います。
ここで疑問に思うのが「自転車で本当に雪原を走れるのか?」でしょう。主にファットバイクと呼ばれるタイヤが太い特殊な自転車を使用することで、この問題を解決しました。
見た目は、マウンテンバイクに似ていますが、タイヤはマウンテンバイクの2倍近くあるぞ。そのようなタイヤを履いているため、雪原だけでなく山道や砂地などでも安定した走りが可能ですね。
近年では、UCI(国際自転車競技連合)により、スノーバイク世界選手権が開催されています。日本では、まだそれほど普及はしていませんが、主なイベントには、「美唄スノーサイクルレース」や「びえいスノーサイクルフェスティバル」などがある。
また、イベントだけでなく、戸狩温泉スキー場のように専門のツアーもあるので、興味がある人はチェックしてみよう。スキーやスノーボードとは、また違った面白さを体験できます。
参加する際には、ヘルメットや手袋、サングラスなど寒さや安全に対応できる装備をしっかりと整えること。そして、天候により状況が刻々と変わっていくので、雪原の状態を事前にしっかりと確認して下さいね。
ライドハンターズ

ライドハンターズは、指定されたエリア内の名所や飲食店などのスポットをたくさん巡り、制限時間内に獲得した総合得点を競うイベントです。
先ほど紹介した「サイクルロゲイニング」に似ていますね。どちらも自転車を使ったアウトドアスポーツイベントであり、両者にはそれほど大きな違いはありません。
しいて言うならば、目的が違うかな。サイクルロゲイニングは、競技性が高くスコアを競う傾向がある。一方、ライドハンターズは特定の場所へ訪れることや、特定の目標を達成することに重きを置いているぞ。
知力・体力・戦略を総動員して、地図を見ながらコースを考えよう。いかにして短時間で効率よくポイントを稼げるかが勝負の鍵となります。
自転車の車輪を使った競技を知っているか?

さて、ここまでサイクリング以外の遊び方を紹介しましたが、今まで紹介したものとはベクトルの違う遊び方を紹介します。
それは、昔から親しまれている「リム回し競争」ですよ。小学生の運動会で体験した人も多いのではないだろうか。
リム回し競争とは、自転車の車輪からタイヤやチューブを取り除き、リムその物の溝に棒を入れて、倒れないように押しながら走る競技。慣れていないと意外と難しく、リムを安定させて進むためのバランス感覚や、カーブを曲がる際の判断が難しい。
それに速く走りすぎると、リムと棒が離れてしまい、思わぬ方向へリムが転がってしまうことも。慎重かつ大胆な行動が必要だったりするので、子供だけでなく大人も熱中しやすいですね。
もともとは、江戸時代に桶からはずれた箍(たが)を回して遊んだことが始まりなんだそうな。そのため、「たが回し」と呼ばれていたという。その後、明治時代に廃物になった自転車の車輪など金属製の輪が使われることになりました。それが発展して、今の競技形式になったそうです。
リム回し競争は、「瞬発力・判断力・バランス感覚」を養うことができるスポーツといえます。
「輪行」は意外に知られていない

自転車を電車や飛行機など公共交通機関へ持ち込める方法として「輪行」があります。
スポーツ自転車を趣味として楽しんでいる人にとっては、良く知られる「輪行」ですが、一般的には意外にも知られていません。
そのため、自転車に興味が薄い人にそのことを話すと、「電車に自転車を持ち込めるだと!!」と驚かれますね。
輪行袋という専用の袋に自転車を収納して持ち込むのですが、この方法によりサイクリングの行動範囲が飛躍的に広がります。
日本国内は鉄道が発達しているので、新幹線や電車を使えば比較的短時間で移動できる。鉄道での移動のため、体力の消耗も避けられるのもいいですね。
また、サイクリング中に疲れたり自転車が故障しても、輪行で公共交通機関を利用すれば、スムーズに帰路につけます。
まとめ

本記事では、スポーツ自転車の意外と知られていない遊び方を紹介しました。最後にもう一度、その遊び方を以下にまとめます。
- サイクルロゲイニング
- トレイルライド
- シクロクロス
- スノーサイクリング
- ライドハンターズ
基本的に自転車は路面を走る乗り物なので、走る環境が変わったり、考え方を工夫することで遊び方も進化します。
ただし安全に遊ぶためには、事前準備をしっかり行うこと。それに加え、サイクルイベントでは、ルールをしっかりと守りましょう。
色々な遊びを体験すると、自転車の可能性や面白さをより知ることができると思います。


