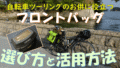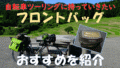四国八十八ヶ所霊場を巡るお遍路の中でも、険しい坂道が続く難所の一つとして知られるのは「太龍寺(たいりゅうじ)」です。
今ではロープウェイを使い移動できるため、難易度は格段に下がりました。標高約600mの山頂近くまで約10分ほどの空中散歩を楽しめます。
ロープウェイを使わなくてもアクセスできますが、ロープウェイからの360度のパノラマ絶景を見ないのはもったいないですよ。
また境内には、荘厳な本堂や大師堂などがあり、豊富なバリエーションの龍が見られるのも面白い。その中でも「龍天井」は必見です。
本記事では、ロープウェイからの魅力ある眺望を中心に、太龍寺の見どころを紹介します。
太龍寺とは

太龍寺は、徳島県阿南市に位置する高野山真言宗の寺院です。
正式名称は「舎心山常住院(しゃしんざんじょうじゅういん)太龍寺」ですね。793年(延暦12年)に桓武天皇の勅願にて阿波の国司・藤原文山が伽藍(がらん)を建立しました。
弘法大師・空海が修業した地として知られ、青年期の空海にとっては、思想形成に多大な貢献を果たしたといいます。
天正年間(1573年~1592年)には、長宗我部元親による兵火により衰退しましたが、その後に徳島藩主・蜂須賀家の保護によって再建されました。
四国八十八ヶ所霊場の第21番札所、阿波秩父観音霊場の第10番札所だけでなく、とくしま88景にも選ばれている景観も素晴らしい。
高山植物が自生しているので、境内をゆっくり見て歩きながら、季節ごと味わいを堪能しましょう。
【神社仏閣の紹介(その1)】
太龍寺周辺にある神社仏閣を、下記記事で紹介します。
道の駅「鷲の里」からロープウェイに乗って太龍寺へ向かう

徳島県内で最も長い河川であり、最も良好な水質として清流四国一にも選ばれたことがある那賀川。
阿南市の山中を流れる那賀川の畔には、道の駅「鷲の里」があります。
駐車場に建てられた石碑には、「川を越え また山越えて もう一つ 往きつく彼岸 太龍の寺」と刻まれており、太龍寺へ辿り着くまでの道のりがいかに大変なのか思い知れますね。
道の駅ということで、レストランや喫茶店、売場、休憩施設などが充実しているので、太龍寺へ向かう拠点として持ってこいですよ。
また、白衣・白装束・金剛杖など主な四国八十八ヶ所巡拝用品がそろっているぞ。

こちらは、観光物産センターの入口前。ここから中へ入り一番奥にロープウェイ乗り場があります。
ロープウェイの年間利用者数は、約10万人なんだそうな。そのほとんどがお遍路さんですね。私が訪れた日も白装束を身にまとった多くのお遍路さんを見かけました。
ちなみに近隣の学校や幼稚園では、太龍寺へ遠足に訪れるといいます。

道の駅にも色々な見どころがあるので、ロープウェイに乗る前に見て回ろう。
たとえば、入口前には日本庭園があり、池の中には鯉が優雅に泳いでいるぞ。う~む、何だか和むな~。

館内へ入ると中央付近には実に見事な「夫婦鷲」が展示されているではないですか。
楠の一途彫りで作られた大作は、まさに魂の一品です。

また、龍のトリックアートもあるので、ぜひ記念撮影にどうぞ。
そんなに寄り道をして「ロープウェイの時間は大丈夫?」という声が聞こえてきそうですが、ご安心して下さい。
こちらのロープウェイの運行時間は以下のようになっており、それほど待ち時間がありません。
- 3月~11月 7:20~17:00
- 12月~2月 8:00~17:00
- 毎時0分・20分・40分の20分間隔で運行
麓から山頂駅までの所要時間は10分ほどです。乗客が多いと臨時便を運行するというのもありがたい。
基本的に年中無休ですが、定期点検のために運休するので、訪れる際には公式ホームページで確認して下さいね。
乗車券の価格は以下の通りです。往復での購入をおすすめします。
- 大 人 片道1,300円/往復2,470円
- 中高生 片道980円/往復1,800円
- 小学生 片道650円/往復1,200円
- 小学生未満の子供は、乗車券1枚につき1名無料
- 15名以上で団体割引きあり
ロープウェイは、西日本最長といわれる全長2,775mもある。1992年から運行されており、このロープウェイのおかげで太龍寺へ簡単に参拝できるようになりました。
ロープウェイに乗り込んだ後は、太龍寺山の山頂付近にある山頂駅を目指して、つかの間の空中散歩を楽しみましょう。
ロープウェイで空中散歩を満喫、雄大な那賀川や田園風景が凄い

ロープウェイのルートは、山と川を越える珍しいもの。そういう意味では貴重な体験ができますね。2つの山を越えて、太龍寺の山頂駅まで約10分ほどで辿り着きます。
眼下には、蛇行する那賀川や田園風景が広がっており、その壮大な景色は目を見開くほど素晴らしい。
ゴンドラは101人乗り込めるほど大きいのもGood。
添乗員が1名付き添うため、道中ではロープウェイから見える景色や太龍寺の見どころについて色々お話を聞くことができるのはありがたいですね。

ゴンドラ内部の足元に注目してみよう。実は一部網になっているところがあり、直接真下を覗けるぞ。
実際中を覗いてみると、これは結構怖いと思うので、高所恐怖症の人は見ない方が良いだろう。(怖さは人によります。)

道中では、他のゴンドラとすれ違ったりしながらドンドン高度が上昇する。そして、山頂へ近づいてくると、目の前にはロープウェイを支える支柱が見えてくる。

一号支柱は高さ42m、二号支柱は高さが24mもあるそうな。それぞれの支柱のそばを通過する際、ガクンと大きな衝撃がくるので、ビックリする人が多そうだ。
ちなみに支柱を通過する前に添乗員から「少し衝撃がきます」という注意があるので、事前に身構えておけば大丈夫だと思います。(私がそうでした。)

眼下に見える山中には、野生の鹿が生息しており、緑一面の大自然を堪能できる。
2号支柱までは、剣山山系の山並みを見渡せて、2号支柱から山頂駅までは紀伊水道や橘湾などの海の風景が見えます。
その他には、ニホンオオカミと弘法大使のブロンズ像が現れてくるのでお見逃しなく。
ニホンオオカミと弘法大使のブロンズ像を見逃すな

ロープウェイの空中散歩コースが、中間地点を過ぎた頃になると、眼下に面白いものが飛び込んできます。
それがかつてこの地に生息していたニホンオオカミのブロンズ像ですね。山犬ヶ嶽に設置された5頭のニホンオオカミ像が、様々なポーズでお出迎え。
聞くところによると、弘法大師も太龍寺での修行中にオオカミの遠吠えを聞いたそうですよ。
私が見かけた時は、山頂へ登っている人もいたので、手を振って挨拶をかわしました。それにしても、山頂に上るとは凄い人もいるもんだな。

また、舎心ヶ嶽には、修行中の大師像が設置さているぞ。かつて空海が、舎心ヶ嶽の岩上で百日間の虚空蔵求聞持法を修したとされているところだ。
山頂駅から歩いて舎心ヶ嶽へ行けるので興味と時間がある方は行ってみよう。
その他には、鶴林寺の三重塔が見えるポイントがありますね。これらのビュースポットは、スポットに近づくと添乗員から話があるので、そのタイミングで窓から眺めるとバッチリ確認できます。
108段の階段を上り本堂へ

山頂駅の外へ出ると、目の前には長い階段が立ちはだかっており、この階段を上った先には本堂があります。
この階段の段数は108段もある。ここで108段と聞いてピンとくる方も多いでしょうね。そうです、108とは人間の煩悩の数です。
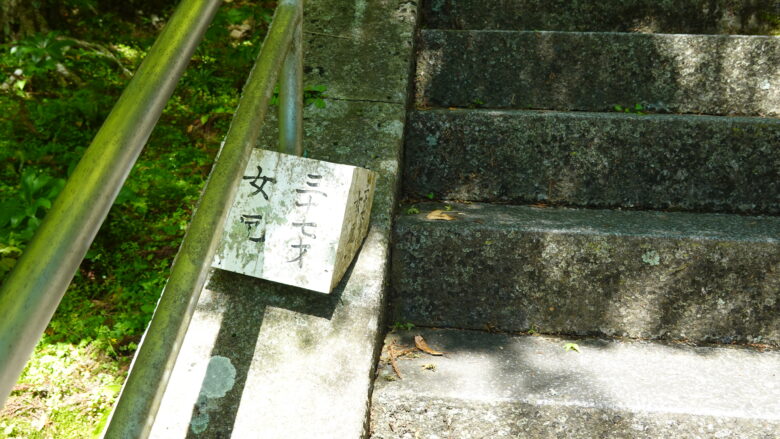

一歩一歩しっかりと階段を歩き煩悩退散としゃれ込もう。階段の端には、所々に小さな石が設置されていて、表面には厄年が刻まれているぞ。段数と厄年をかけているのだと思う。
そして100段目には「100歳おめでとう」と祝ってくれます。
階段を上る際、真ん中寄りに上ると気付きにくいかも知れないので、少し端寄りに上ってみて下さいね。
持仏堂の「龍天井」は必見、その他にも境内には龍がたくさんいる

寺務を取り仕切り、僧侶が寝泊まりする場所が持仏堂(本坊)です。
1894年(明治27年)の火災で焼失しましたが、再建され今に至ります。空海が行った虚空蔵求聞持法を修行する道場として、重要な建物なんだとか。
そんな持仏堂では、外からたくさんの龍の置物などを見物できる。その中でも目玉となるのが「龍天井」だろう。

お堂の正面から覗ける大廊下の天井には、大迫力の「龍」の天井画が活き活きと描かれています。
この天井画は、高知出身の明治時代の日本画家・竹村松嶺の作品。目の玉が大きくて、すごい眼力を感じるぞ。
消えかかっている部分が気になりましたが、長い時間が経過したため仕方がないのかも知れませんね。

そもそも神社仏閣では、龍の彫刻を見かける機会は多く楽しませてくれます。太龍寺では、見かける龍のバリエーションが豊富ですよ。

たとえば、手水舎には仲良く並んだ首だけの龍がいるなんてかなりレア物だ。
境内をじっくり見て回り、どんな龍と出会えるのか楽しみにしておこう。
【神社仏閣巡りに役立つ話】
神社仏閣巡りに役立つ様々な話を、下記記事で紹介します。
荘厳な本堂と多宝塔

本堂は1852年(嘉永5年)に阿波藩の藩主・蜂須賀公によって建てられました。
国の登録有形文化財に指定されており、歴史を感じる荘厳さが魅力的。
弘法大師が彫った虚空蔵菩薩を本尊として安置されています。知恵や幸福などあらゆる人々の望みを叶えてくれるというありがたい仏様ですね。
四国八十八ヶ所霊場の御本尊に虚空蔵菩薩が祀られているのは、太龍寺・焼山寺・最御崎寺の三カ所だけ。そう考えるとレアな御本尊といえるかな。
普段はその姿を拝めませんが、毎年1月12日の初会式にご開帳されます。

本堂の彫刻は、龍や飛び出す獅子など見応えあり。なのでじっくり見物していこう。また、本堂の内部には、なで仏の「びんずるさん」や大きな赤いダルマがいるぞ。

本堂の北側にある高台へ向かうと多宝塔を発見。この多宝塔は1861年(文久元年)に建立されており、五大虚空蔵が安置されています。
五大虚空蔵は災いを防ぎ、招福のご利益があるというのだから、太龍寺の中でも人気スポットになっている。
特に60年に1度行われる除災祈願は、盛大に執り行われるそうな。天変地異の災いを取り除くご利益があるというのだから、スケールが大きいですね。
【神社仏閣の紹介(その2)】
旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。
仁王門には徳島最古の仁王像がいる

太龍寺の仁王門は、1806年(文化3年)に造られた表玄関に相応しい重厚な造りが見事です。
この仁王門は、ロープウェイを使用しないルート側にあり、本坊よりもさらに東側にあるため、スルーしてしまう人がそれなりに多いと思う。

本坊から仁王門へ向かう参道は、参道の中でも一番の急勾配となっていました。
本坊から下り道ですが帰りは反対に上り坂となる。それを考える躊躇してしまうかも。けれど徒歩約2分ほどで辿り着けるので、たいした距離ではありません。

仁王門の両側の格子からそっと仁王様(金剛力士像)を拝見して下さいね。
この仁王像は、鎌倉時代に作られ徳島県で最大で最古のものなんだとか。せっかく太龍寺へ参拝にきて、見逃すのはもったいないです。
四国霊場でトップクラスの大きさを誇る「大師堂」

太龍寺の大師堂は、御廟の橋や拝殿、御廟などの並びが高野山奥の院と同じ配列になっています。これが「西の高野」と呼ばれている理由ですね。
私が訪れた時は丁度、大勢のお遍路さんが一斉にお経を唱えていたのが印象的でした。
この大師堂は、四国霊場の中でもトップクラスの大きさがあり、彫刻も見事なり。個人的には、本堂よりも大師堂の方が気に入ったかも。


彫刻を見てみると龍は当然いるとして、猛獣の首を押さえつける勇士など興味がそそられるものが多いですね。
これらの彫刻は、全て中国の神話や民話がモチーフになっているという。実際どんなお話なのか、私気になります。
また、弘法大師の十大弟子が壁に描かれていたり、白虎や青龍などの四神が配置さているので隅々まで見物していこう。
【神社仏閣の紹介(その3)】
旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。
舎心ヶ嶽の遥拝所でお参り

山頂駅から外へ出て、すぐ左手側に舎心ヶ嶽(しゃしんがたけ)の遥拝所があります。
舎心ヶ嶽は、弘法大師が19歳の時に虚空蔵求聞持法修行をしたという聖地ですね。太龍寺の奥の院になっています。(奥の院は全部で3つあり)
この遥拝所の近くには、舎心ヶ嶽へ向かう道が続いているのですが、距離が約680mほど離れていることもあり、スルーする人は多いと思う。
かくゆう私も時間の都合で行けなかったので助かりました。

遥拝所からは、うっすらと修行時代の大師像が見える。そこで、カメラのズーム機能を使って撮影すると、大師像があるのがハッキリと分かるぞ。

ちなみに、こちらが舎心ヶ嶽へ向かう道の入口です。
興味と時間がある方は、ぜひチャレンジしてはいかがですか。
【神社仏閣の紹介(その4)】
旅先で訪れた神社仏閣を、下記記事で紹介します。
太龍寺には珍しい「相輪橖」が現存する

太龍寺には、日本のお寺に数ヶ所しか現存しない「相輪橖(そうりんとう)」があります。
相輪橖は仏塔の一種であり、三重塔や五重塔の屋根の部分を取り払い柱と仏塔の屋根の上にある相輪の部分からなっている。
太龍寺の他には、比叡山延暦寺や日光山輪王寺などでしか見られないレアな塔なのでお見逃しなく。
太龍寺の基本情報とアクセス
| 住所 | 徳島県阿南市加茂町龍山2 |
| 電話番号 | 0884-62-2021 |
| 納経所対応時間 | 8:00~17:00 |
道の駅「鷲の里」までのアクセスと駐車場
道の駅「鷲の里」には、無料駐車場があります(普通車 150台)
- JR桑野駅から徳島バス丹生谷線に乗って「和食東」のバス停で下車後、徒歩約10分(バスの乗車時間は約20分)
- 徳島市内(県庁)から車で約60分
まとめ

「遍路転がし」の異名がある太龍寺ですが、ロープウェイのおかげで難なく辿り着けます。
ロープウェイからは360度のパノラマ絶景を楽しめ、特に雄大な那賀川や田園風景が素晴らしい。天気の良い日にぜひお出かけしてみよう。
それに「西の高野」と呼ばれる太龍寺は、四国霊場の中でも壮大なスケールを誇る。境内は広いので、ゆっくりと見て歩くならば、所要時間は1時間から1時間30分ほどかかります。
清涼な空気を味わいながら、修行に明け暮れた弘法大師空海の思いを肌で感じて下さいね。