
サイクリングへ出かける際、できるだけ荷物をリュックに入れて背負って走りたくないですね。
短時間ならばともかく、長時間背負っていると背中がむれてきたりします。また、重い荷物を背負っていれば、肩や腰に負担がかかるため嫌なものです。
これらの問題を解決する手段として、サドルバッグの利用を思いつく人は多いでしょう。
けれど、各メーカーから大小様々なサドルバッグが販売されており、どれを選べば良いのか悩んだりしませんか。
本記事では、サドルバッグを選ぶポイントや最低限入れるものを含め、後悔しないサドルバッグの選び方を解説します。
後悔しないサドルバッグの選び方

サドルバッグとは、自転車のサドル下に取り付け、必要な物をコンパクトに持ち運ぶためのバックです。
取り付けが簡単なものが多く、小物を入れるのに丁度よいものから、キャンプ道具などを運べる大型のものまであります。
サドルの下に取り付けるため、フレームに余計な負荷をかけるものが少なく、カーボンフレームのロードバイクでも安心して使えるのは嬉しいですね。
また、車体の見た目を損なわないデザインや、走行中に邪魔にならないことから使い勝手が非常によい。
そのため、ロードバイクやクロスバイクに乗っている方が、愛用しているケースが多いです。

サドルバッグの最大のメリットは「バッグのサイズしだいで大きな荷物も運べる」につきます。
なので一番重要なのは、バッグの容量ですよ。何をバッグに入れたいかによって容量やサイズが決まってくる。
普段のサイクリングや日帰りツーリング、ロングライド、キャンプツーリング、自転車旅などによって運びたい荷物は人によって様々。
容量やサイズ以外にも選ぶべきポイントは多いので、以下にサドルバッグの選ぶポイントをまとめました。
- 容量やサイズの確認
- シートポストの突き出しの有無
- バッグの固定方法
- 防水性の有無
- テールライトを取り付けられるか
- バッグが後輪に接触しないか
- 太ももに接触しないか
それぞれについて説明します。
【ポイント①】容量やサイズの確認

普段のサイクリングや日帰りツーリングでしたら、サドルバッグで持ち運ぶのものはそれほど多くありません。
具体的にいえば、パンク修理に必要となるアイテムと携帯工具で十分です。すると小容量のサドルバッグが1つあれば、収納できますね。
小さいサイズのサドルバッグは、あまり目立つことなく邪魔にもならないので、毎日のサイクリング用に常にサドルバッグを付け続けるのもよい。
また、月に数回程度の日帰りツーリングの時だけ、バッグを取り付けてもよいでしょう。

ロングライドやキャンプツーリング、自転車旅になるとそれなりの荷物を運ぶことになる。すると、運ぶ荷物の数や大きさに応じて、サドルバッグも大容量になるものです。
1.5L程度の容量があれば、1泊2日の衣類も収納できることが多い。1日フルに走って何日も宿泊し、様々な天候に備えたいのならば10Lの容量が目安になります。
キャンプツーリングや自転車旅などで、テント一式や調理器具、衣類など多くの荷物を運ぶ場合は、サドルバッグ1つでは足りないことが多いですよ。
そういう時は、サイドバッグやフロントバッグなど他のバッグと組み合わせて使いましょう。

ちなみに私が使っている大型サドルバッグは、オルトリーブのサドルバッグ2です。容量4.1Lもある優れもの。いまや自転車旅に欠かせないバッグになっています。
【ポイント②】シートポストの突き出しの有無

大容量のサドルバッグの中には、シートポストからかなり突き出しているものも多いです。
突き出しが大きすぎると、シッティングやダンシングなど走りに影響を与える場合が多いので確認しておきたい。
特に身長が低くて、シートポストの突き出し量が少ない場合は、大容量のサドルバッグを取り付けられないことがある。
大型サドルバッグは、物によっては1万円を越えたりしますので、失敗すると精神的ダメージが大きいですね。
できれば自転車ショップなどで、現物があれば見せてもらえると安心します。
【ポイント③】バッグの固定方法

サドルバッグの固定方法は、ベルクロベルト式とアタッチメント式の2種類がほとんどです。
ベルクロベルト式は、サドル下のレールとシートポストの2点をマジックテープで固定する方法のため、取り付けに工具を必要としません。
位置の微調整もかんたんにできるため、お手軽に利用できます。
アタッチメント式は、サドル下に工具で台座を取り付けるため、最初のアタッチメントの位置出しが結構難しかったりする。
けれど、一度アタッチメントを設置すると、常に同じ位置にサドルバッグを固定できるだけでなく、サドルバッグ自体の脱着がしやすいため、使い勝手が非常によくなります。
ちなみに私が愛用しているオルトリーブのサドルバッグ2は、アタッチメント式ですね。私のように輪行をする機会が多い場合は、アタッチメント式が向いているでしょう。
【ポイント④】防水性の有無

サドルバッグの防水性は、中に入れるものによって重要性が変わってきます。
特にスマートフォンなどの電子機器や財布を入れるのならば、防水性や撥水性に優れたものがおすすめです。雨が降っていても、バッグの中まで濡れる心配をする必要がありません。
たとえ雨の中を走らなくても、路面が濡れていたり、雨水が溜まっている路面を横切るなんて普通にある。
水や泥などの跳ね返りがあったとしても、防水性であれば安心感があります。
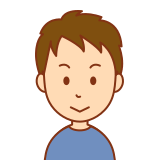
あらかじめ自転車にフェンダーを装着していれば、濡れた路面を通過したとしても、多少の水や泥などの跳ね返りは防いでくれるよ。
【ポイント⑤】テールライトを取り付けられるか

自転車のテールライトは、大抵のものがシートポストに取り付けるタイプですね。町中を走るロードバイクやクロスバイクを目撃すると、サドルの下部付近に付けている人を多く見かけます。
サドルバッグを取り付けてしまうと、テールライトを付ける場所がなくなってしまう可能性が高い。なので、テールライトをどこへ取り付けるのかが問題になってくる。
サドルバッグの中には、テールライトを取り付けられるものもあるので安心して下さい。もし取り付けができなくても、最低でも反射板がついているものを選ぶべきです。
尚、テールライトによっては、シートポスト以外の箇所にも取り付けられますね。
サイクリング中の事故を減らすためにも、できるだけテールライトは装着しましょう。
【ポイント⑥】バッグが後輪に接触しないか

小容量のサドルバッグでは、あまり気にする必要はないのですが、大容量のサドルバッグになると、後輪に接触しないか必ず確認して下さい。
特にサドルの高さが低い方やフレームサイズが小さい方は、サドルと後輪の間の隙間が狭いことが多く、バッグの底面がタイヤと干渉し、走行に悪影響を及ぼします。
さらにバッグの底面が擦り減り、穴があいてしまうかも知れません。これらの理由により、大容量のサドルバッグの取り付けを、諦めなければならなくなる。
一般的にサドルと後輪の間の隙間は、20cm以上が必要といわれていますが、バッグの形状によっては、それ以上に必要になることも。
尚、バッグの中に荷物を入れた状態で、サドルと後輪の間に十分な隙間があるのかを確認するのがポイントです。たとえ隙間があったとしても、わずかしかなければ、走行中の振動などでバッグが沈みタイヤに接触してしまう可能性があります。
【ポイント⑦】太ももに接触しないか

大容量の大型サドルバッグを取り付けた際、サドルからはみ出さないようにしましょう。
はみ出した状態のままで走行すると、太ももが干渉してしまい、走行に悪影響を及ぼします。なので、事前に干渉しないかのチェックは重要ですよ。
サドルバッグの中身を入れる際、バッグ先端に物を詰めこむと、先端が膨れてしまう可能性がある。それが原因で太ももが干渉したりするので、物の入れ方を工夫しましょう。
サドルバッグの中に最低限入れるもの

サドルバッグに入れるものは、サイクリングや自転車旅などの目的に応じて人それぞれですが、最低限入れるべき道具(アイテム)を以下に挙げます。
- 予備チューブ(できれば2本)
- タイヤレバー
- パンク修理キット
- 携帯工具
- CO2ボンベ+アダプター(携帯ポンプがあれば要らないかも)
- 鍵
ほとんどがパンク修理に必要なアイテムばかりですね。これらの物は、小容量のサドルバッグに入るし、ボトルケースやボトル缶に入れることもできる。そのため、ボトルケースを使うならば、普段のサイクリングにサドルバッグがなくても対応できます。
けれど、ボトルケースやボトル缶を使うとボトルゲージを1つ使ってしまう。それを避けたいのならば、サドルバッグを使いましょう。
サドルバッグの紹介

各メーカーから様々なサドルバッグを販売していますので、おすすめのサドルバッグを下記関連記事で紹介します。
まとめ

本記事では、サドルバッグの選び方について説明しました。
最後にもう一度、サドルバッグを選ぶポイントを以下にまとめます。
- 容量やサイズの確認
- シートポストの突き出しの有無
- バッグの固定方法
- 防水性の有無
- テールライトを取り付けられるか
- バッグが後輪に接触しないか
- 太ももに接触しないか
サドルバッグは、普段のサイクリングや日帰りツーリング、ロングライド、キャンプツーリング、自転車旅など様々なシチュエーションをこなせて、体の負担を軽減できるアイテムです。
用途に応じて適切なサドルバッグを取り付けて、快適なサイクリングを楽しみましょう。


